まえのページへ
機能性ということは
機能性という言葉がよく使われます。
一般的には、機能性という意味は、
必要とする良い効果をプラスするときに使用されるようです。
マイナスの効果のときには、使用しないようです。
例えば、普通の紙は折り曲げるとそのままの形を継続しますが、
折り曲げても手を離すと、自然と元に戻る(選挙投票用紙)とか、
水にぬれても、とろとろにならない性質をもっているので、
雨の中でも記入できる(雨の防災訓練などで使用可能)とか。
また、食品などでは、栄養や味だけでなく、
生態調節機能を強調した食品であったりします。
食物繊維を入れて、便通を良くし、
腸の掃除をしたりする場合に使用されており、
機能性食品などと言われています。
ヘルメットにも機能があります
作業現場などで着用するヘルメットにも、
いろいろ機能を付したものがあります。
第一の機能は、物体の飛来・落下による危険を防止するや激突防止の「飛来・落下物用」、
第二の機能は、墜落・転落による危険を防止する頭の保護を主とする「墜落時保護用」、
第三の機能は、感電防止の効果も備えた電気による危険を防止する「電気用」です。
労働安全衛生法上の保護帽の着用規定では、
「飛来・落下物用」は、物体の飛来落下の恐れのある場所における
作業等での着用を義務付けています。
「墜落時保護用」は、最大積載量5t以上の大型貨物自動車における荷の積み卸し作業、
2m以上の高所作業等での着用を義務付けています。
「電気用」は活線作業等で使用することが規定されています。
このように、ヘルメットには3種の機能がありますが、一般の企業では、
衝撃吸収材を内装した墜落用保護帽を飛来落下物用と
兼ねて使用している場合が多いのではないでしょうか。
機能は正しく使われるひとによって発揮される
ヘルメットの中には、「内装体」というものがあります。
「内装体」には、着用者の頭のサイズに合わせるための「ヘッドバンド」がついており、
「ヘッドバンド」にはサイズの調節部があります。
 また、保護帽の頭部への当たりを良くし、
衝撃吸収の役目をもつ「ハンモック」がついています。
さらに、各人の頭の大きさ合わせ取り囲む「環ひも」からなっています。
「環ひも」はプラスチックで一体となっています。
そして、保護帽の脱落防止の役目をもつ、「あごひも」がついています。
墜落時保護用としては、二輪車用の安全帽に同じく、
帽体と内装との間に衝撃吸収用の発泡スチロールの「衝撃吸収ライナー」が入れられています。
一方、電気用保護帽については、労働安全衛生規則第351条において
「六月以内ごとに一回、定期的にその絶縁性能について自主検査を行わなければならない」と
定められています。
また、保護帽の頭部への当たりを良くし、
衝撃吸収の役目をもつ「ハンモック」がついています。
さらに、各人の頭の大きさ合わせ取り囲む「環ひも」からなっています。
「環ひも」はプラスチックで一体となっています。
そして、保護帽の脱落防止の役目をもつ、「あごひも」がついています。
墜落時保護用としては、二輪車用の安全帽に同じく、
帽体と内装との間に衝撃吸収用の発泡スチロールの「衝撃吸収ライナー」が入れられています。
一方、電気用保護帽については、労働安全衛生規則第351条において
「六月以内ごとに一回、定期的にその絶縁性能について自主検査を行わなければならない」と
定められています。
しかし、大事なことは、これらの取付け部品を備えてはいますが、正しく着用しなければ、ヘルメット本来の機能を発揮しないということです。
この機能を発揮するためには、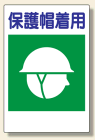 ①頭の天辺が、環ひもにあたるように被る。
①頭の天辺が、環ひもにあたるように被る。
②頭部の調節具によって、ヘッドバンドの径を、自身の頭部サイズに調節し、固定する。
③後ろに傾けないで、真っ直ぐに被る。内装の下辺が眉の上に来るぐらいが適当。
④墜転落時の脱げ防止のために、あご紐をきちんと締める。
以上が正しい被り方ですが、不適当な着用例としては、
①帽子などを後ろに傾けた阿弥陀被りをする。着用の様子が、
体の後ろから発せられる光を現した、光背をまとった仏像に似ていることから
このようによばれている。
②あごひもを締めてない被り方をする。だらしなくも見られる。
1メートルは一命をとるとも言われ、ヘルメットが脱げて、死亡して例がある。
③ヘルメットの天辺にあご紐をまわして止めるのはもってのほか。
ヘルメットは正しく着用をしなければ、災害に直面したときに全く役にたちません。
見て見ぬふりをするとだめです
以前、ある大会社の安全活動の取り組みが雑誌に載っていましたが、
何枚かの安全活動を撮った写真の中に、阿弥陀被りをした社員の写真が出ていました。
いくら、安全活動を社外にアピールしてもこれでは見る人がみたら疑問に感じるのではないかと思いました。
同じように、我が社は品質保証は万全ですなどと言いながら、工場を案内したときに、
ちゃんとヘルメットをかぶっていない従業員を見かけるようでは、
社員教育が出来ていないと、いくら説明を丁寧にしても信用して貰えません。
品質システムの教育も重要ですが、身だしなみの教育も重要です。
教育ができていないのに要求品質のものが果して作れるのかと疑われるでしょう。
なぜなら、安全も品質も根っこは同じだからです。
3即で対応(即時、即座、即応)
確かに、ヘルメットをちゃんと被っていなくても、歩行するだけなら、
一生涯で、怪我に合う確率は、宝くじに当たる確率以下かもしれません。
しかし、小さなことが、守れない人は、その他の重要なことも守れません。
これぐらい、いいじゃないか、それは止めなければなりません。
小さなことを守って初めて、ほかの安全の基本も守られます。
違反を見かけたら、その場で、すぐに是正の行動が必要です。
間髪(かんはつ)を容れず注意することが求められます。
この、語源は、間に、髪の毛一本も入れる隙間を置くこともなく行うということですが、
安全に関しては、同じように、遅れは許されません。
即時、即座、即応での対応が必要です。
あご紐は部屋を出てからからではなく、ネクタイを締めるような気持で、
着用したらすぐにあご紐を締め、きちっと被る習慣づけが基本です。
そして、日頃のコミュニケーションを高めておくこともあわせて重要です。
人に注意されて、素直に聞ける場合と、反対に此畜生と思う場合があります。
重要なのは安全への思いが素直に伝わる人間関係かと思います。